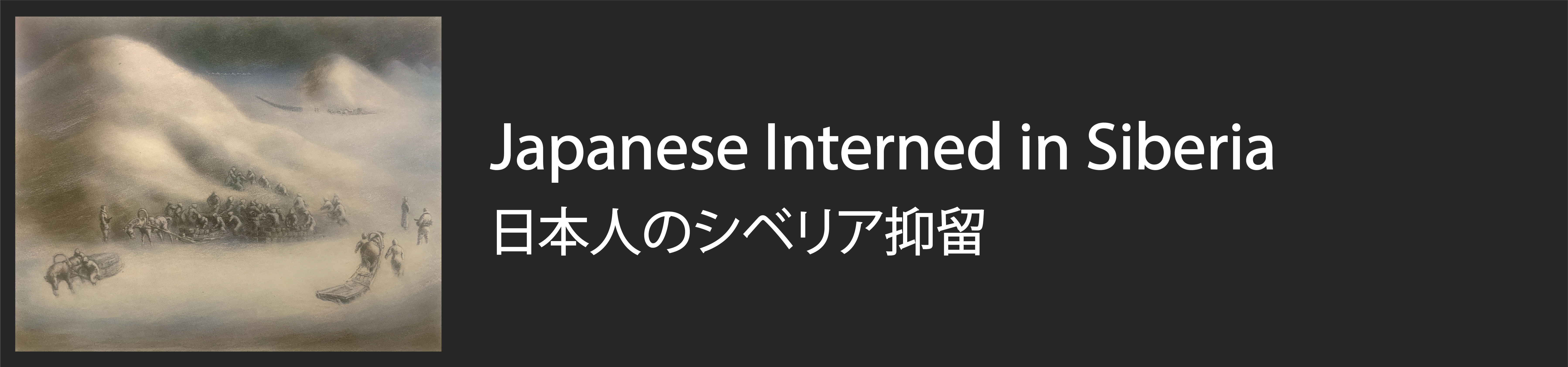情報通信社「フェルガナ・ニュース」 http://www.fergananews.com/articles/6203 2009年6月15日
(2009年当時より約)60年前、最後の日本人抑留者(*注1)がタジキスタンを去っていった。しかしいったい何故日本人がこの地に送られ、そして帰国に至ったのか? 語れる者がまだタジキスタンにいた。日本人がタジキスタンでいかに暮らし、何を食べ、どこで強制労働に従事していたのか。そして祖国の土を踏むことなくタジキスタンで亡くなった日本人将校と兵士がどこに埋葬されているのか、その事実を追った。
取材を続けていくと、スピタメン地区プロチナ村(*注2)にたどりついた。この村で多くの日本人抑留者が、ファルハド水力発電所建設の強制労働に従事していたとされる。
-1940年代半ばに9つの水力発電所建設プロジェクトが立ち上がっていた。その一つで通信士として働いていた(2009年当時)82歳のアレクサンドル・ズーボフ氏が回想する。
「日本人抑留者たちは、1945年8月中旬から9月下旬までの1ヶ月半にわたって連行されてきた。抑留者たちは、事務棟、居住棟、工場、道路、ダム建設、電線架設、工場内労働に従事していた。
アレクサンドル・ズーボフ氏
ドイツ兵捕虜と同様、彼らの抑留生活は長い年月に渡った。主に将校や兵士からなる日本人抑留者約5千人が、マールィ水力発電所地区、兵営地区、シーリン町(*注3)地区収容所内での生活を強いられていた。日本人のほかにドイツ兵捕虜も収容されていたが、今や誰もその人数について知る者はいない。しばらくしてドイツ人達は、他の工業地区、噂によれば、秘密都市タボシャル村の住宅建設か、ウラン鉱採掘現場へ送られたという。
25歳から45歳までの日本人抑留者たちが、労を惜しまず懸命に働いていた。
スピタメン地区ゴールヌィ村(*注4)に採石場があり、その石材が、ファルハド水力発電所(*注5)堤体工事やシルダリア川護岸工事に使われていた。建設機械など何ひとつなく、日本人たちは、手押し一輪車に石を載せ運搬した。・・・抑留生活に耐えきれず、ダムの上から投身自殺、割腹自殺する日本人もいた。」
-1945年当時、前線から警備員として復員、プロチナ村在住、90歳(2009年当時)のアブドラヒム・ミルボボエフ氏も証言者のひとりである。
「当時ファルハド水力発電所建設工事が急ピッチで進められていた。最も責任重要かつ困難な作業が日本兵に任されていた。日本兵は非常に知性豊かで創造力に富み、手抜きなどせず正直かつ誠実に労働と向き合っていたからであろう。また日本人は、ダムと護岸強化工事の他、二つの運河を建設した。この二つの運河は、現在まで修理することなくダムの水量調節に利用されている。
重要な点は、この運河トンネルから一滴の漏水もないことだ。日本人が正しい計算を行い、いかなる欠陥も許さなかったからである。そのおかげでファルハド水力発電所の稼働後ダム水位下となったサイドクルガン村、ファルモンクルガン村、オクテッパ村、クルク村等は洪水被害を克服することができた。
日本人抑留者が建設したタジキスタン北部の運河
日本人抑留者が建設したタジキスタン北部の運河
-日本人がプロチナ村に到着したのは、1945年8月~9月で、1950年代初めまで強制労働に従事していた。その間、芸能人たちが何度か、有名なタマーラ・ハヌム (注:民族舞踊女性歌手)率いる一団も、抑留者たちの慰問にこの地を訪れた。
日本人の帰国を見送る際には、新たに芸能人を呼びよせ、鉄道駅まで音楽を奏で見送った。日本人は皆泣いていた。
やっとの「ダモイ」帰国への旅路が叶い喜びに涙する者、生きて祖国へ向かうことなく異国の地で眠る多くの友との別れに涙する者がいた。・・・
―プロチナ村で何人の日本人が亡くなったのか知る者はいない。1958年ソ連邦内務省刑務所統括部長ブラノフはタジク共和国内務省に対し、日本人抑留者埋葬墓地処分に関する命令書を発出した。「墓地を処分する際、埋葬地の土饅頭を平らにし、墓標と柵を破棄すること。処分した墓地の土地は、コルホーズ、ソフホーズ等の地元の地主へ譲渡し、譲渡に関する公式文書を発行すること。」
-おそらく日本人は、収容所内、マールィ水力発電所区域内ならびにファルハド水力発電所区域内に埋葬されているはずだ。しかし、正確には何も知らない。当時スターリンの命令は全て機密扱いだった。」
-地元の報道関係者ラフシャン・カシーモフ氏によれば、日本人強制抑留者収容所は現在のスピタメン地区ハシチアク村(*注6)とクルカト村に存在していたと推測される。
「当時いた日本人達は、自らを戦争捕虜ではなく抑留者であると認識していた。日本人としての誇りが、捕虜の身分を受け入れることを許さなかったためであろう。日本兵は、勝利もしくは戦場での誇り高き死のみが許されていると信じてていたからだ」
********
すでにおびただしい数の犠牲者がでていたにもかかわらず、日本人は最後の一人まで、ソ連と戦う覚悟だった。しかし1945年8月15日(*注7)天皇陛下より「終戰の詔勅」が発せられ、アジア・太平洋前線で死闘を繰り広げていた日本軍人は、武器を捨て投降するほかなくなった。そのため比類なき数の日本兵と将校が捕虜となった。
日本人抑留者の埋葬地を発見し、その地に慰霊碑を建立することが、現在そして将来の重要課題である。日本人は強制収容所内で不自由な生活を送りながらも、国家経済発展に重要な役割を果たす国民生活に必要な数多くの堅牢な施設の建設を行い、その記憶を我々に残したからである。戦後の困難な時代、日本人は強制にもかかわらず、自らの正確で組織的かつ良心的労働によってソ連邦に多大な援助を行った。そして現在、日本政府はタジキスタンを含む発展途上国に対し無償資金協力・技術協力を行っている。
専門家の意見によれば、日本はタジキスタンの潜在的パートナーである。両国には多くの共通点がある。タジキスタン人は、今も感謝をもって記憶にとどめる。日本人がタジキスタンに抑留されていた五年間、ただの一度も地元民とのいさかいがなかったことを。ただの一度も…。
チラフ ラスル・ザデ
注1:当協会趣旨に従い、原文ロシア語句「戦争捕虜」は、その大部分の和訳を「抑留者」に改めた。また、食事を含む待遇、生活についての記述は、日本人抑留者の「労苦」証言と隔たりが大きいため省略した。またコメルサント紙からの引用文も省略した。
注7: 原文中は8月17日との記載であったが、8月15日に改めた。
注2: プロチナ村-「プロチナ」は、「ダム」を意味するロシア語。タジキスタン共和国ソグド州(旧レニナバード州)スピタメン地区(1929年ソ連ウズベク共和国からタジク共和国へ移行)の村。人口は、タジク系約650人に対しウズベク系約1500人で、国境線のドゥストリンスク運河北対岸ウズベキスタンに経済、行政さえ依存しているとされる。
注3:シーリン町- ウズベキスタン共和国シルダリア州の町。ベガワード(ヒルコフ)駅東方約7キロ
注4:ゴールヌィ村-ファルハドダム北西に位置するウズベキスタン国境タジキスタン側の村。住民のうちウズベク系は約500人とされる。
注5:ファルハドダム―ダムのコントロールはタジキスタンが行なっているが、ダムを利用した水力発電所はウズベキスタン側にあり、ウズベクエネルゴが運営を行なっている。Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%83%89%E3%83%80%E3%83%A0
http://homepage2.nifty.com/silkroad-uzbek/works/2009/27.html
注6: ハシチアク村-ベガバード(ヒルコフ)駅より地図上で南方約4キロ。タジキスタン、ソグド州(旧レニナバード州)内の集落。かつてベカバードに住む人々に自家製乳製品を届ける農村であった。
http://wikimapia.org/#lang=ja&lat=40.214276&lon=69.263992&z=12
ソ連における日本人収容所位置概要図 (「戦後強制抑留史」第7巻 資料編 283 p.)
*上記地図では、「ベグワード」駅と「ヒルコフ」駅の位置が異なっている。