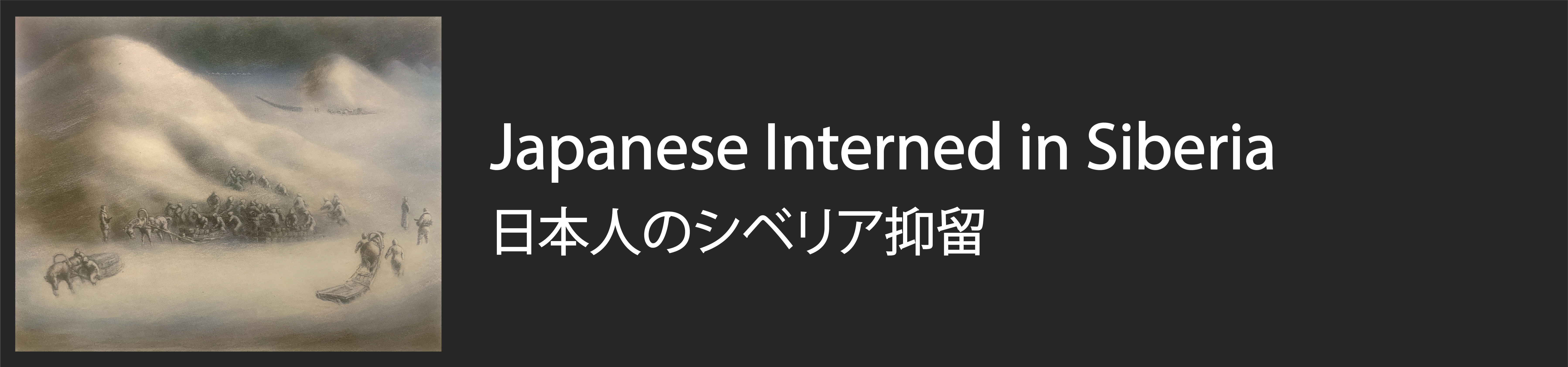さて、馬橇に乗り三日後、寂しげなベイ村という所に着き、赤羽さんは大きな丸太小屋を四つ五つに仕切った部屋にダーシャというロシア人と一緒に住むことになった。そこでは自分で働いて生活費を捻出しなければならなかった。掃除婦の仕事があったのだが、きゃしゃな体の赤羽さんには厳しすぎた。半年間の移動の旅の間にすっかり精力を使いはたして、三十七キロの体重が、五、六キロは減ってしまっていた。その時ウクライナの女のたくましい腕がどれほど羨ましかったことか…。それで生活の糧は刺繍の仕事となった。
ある日ダーシャと一緒に村の店から、穴倉のじゃが芋の選別を頼まれて出かけた時のことを赤羽さんは次のように書いている。食料の困窮と将来への不安がうかがわれる。
「穴蔵は寒く、暗い。泥まみれのじゃが芋はほとんど凍っているが、その中から腐った芋を選り分けていく。選っても選っても、芋の山はなかなか小さくならず、石油ランプの乏しい灯で目がちかちかして来る。ダルマストーブの暖気でとけた芋の土が、べとべと手につく。穴蔵の中でなら、芋は食べ放題という条件だったので、昼はストーブで芋を焼いて食べた。一度凍った芋は、皮が赤味を帯び、さつま芋のように甘くて、私は好きだった。夕方になると、ダーシャはよさそうな芋を体の方々に隠した。長靴の中にまで入れた。私は盗みは嫌いだったが、ダーシャの機嫌を損ねることも煩わしかったので、何個かを服の中に入れた。芋の泥が身体について、いやな気持ちだった。1951年の正月三が日は、こうして芋の選別に明け暮れた。私の頭には、仕事のことが絶えず重くのしかかっていた。手持ちの百ルーブルのお金では居食いしようにも先が見えている。頼みの刺繍も、みなが最低生活をしているようなこの村では、どうも期待薄のように思われた。(p.203)
このエニセイ河のほとりの村には四百人の住人がいて、その内百人が流刑人、その他は自由人であった。川岸には貯木場があって、長い冬の間河が凍っている。その河と森だけがベイ村のすべてであったので、村の男たちはほとんど森林の伐採を仕事としていた。女でも森で働き、よい給料をもらう者もあった。
流刑人達はこの場所を出ることを許されていなかったので、これは日本に昔あった「島流し」のような生活だった。耐え難い生活の現実ではあったが、かろうじて共に生きる仲間がいたので、流刑の人たちは頼り合って生きていた。流刑人はロシア人のほかに、ウクライナ人、ポーランド人、ラトビヤ人、グルジヤ人、ドイツ人、中国人、朝鮮人、フィンランド人。そして日本人は赤羽さんただ一人。その中には住み慣れた我が家から突然強制移住された人もいて、そんな人達は、急激な生活の変化と自由の喪失に途方に暮れていた。より過酷なラーゲリ生活を経てきた赤羽さんには、既に慣れていた環境だったので、その人達をとても気の毒に思った。