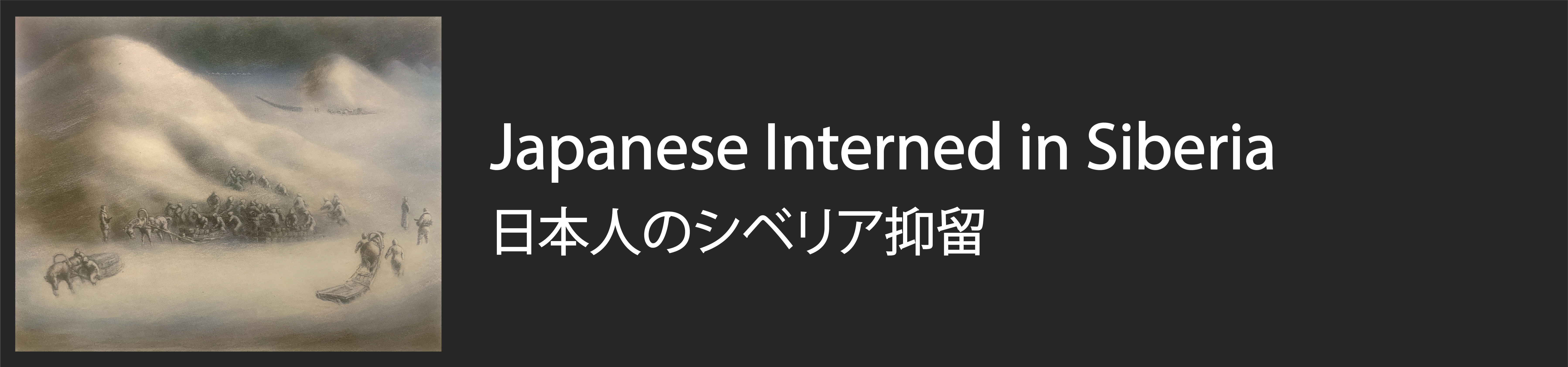赤羽さんは、次は奉天(現在の瀋陽)の元三井ビルの臨時監獄に連れて行かれた。そこではトイレに困った。部屋の隅のバケツに用を足し、朝夕二回自分でトイレにそれを空けに行くのだ。また、真夜中に酔っ払った看守が同室の中国人の女性を連れ出すという恐ろしい経験もあった。1900年頃の帝政ロシアであったように、ソビエト連邦でも看守や監視の兵隊の女囚への暴行、強姦はほしいままにされていた。その奉天の監獄にいた三ヶ月の間入浴は一度だけだったので、虱にもひどく悩まされていた。それから詰め込まれたのは馬の輸送車で、息も詰まるほどの馬の匂いの中での日課は虱取り。何日進んでも、雪と氷だけで、やがて列車はソビエトへと向かっていることに気づいた。のろのろの列車の便所の窓から脱走した中国人二人が捕まり、銃殺されるという事件もあった。17日目になって汽車は泊まると、そこには雪だらけの場所に何百、何千の日本人捕虜たちがいた。その中で女は三人だけ。すぐに赤レンガの建物に収容され、また囚人護送用のトラックに詰め込まれ、次に降りたところはチタの監獄であった。そこで赤羽さんは、荒れ放題の部屋へ入れられた。所持品検査があり、布団と衣類だけ残されたが、その時熱が38度以上あったため、病院へ入れられることになった。そこまでの苦しい旅の途中、親切にしてくれた日本人達との悲しい別れだった。一人病院へ向かった赤羽さんには、この別離が以後10年にわたって二度と日本人には会わない苦難のひとりぼっちの戦いの始まりとなった。(p.27)
数日後、風呂敷一つだけの私物を一人でひきずって、赤羽さんは監房へ戻った。「長い長い廊下や、階段をいくつも通った。重たく閉ざされた鉄の扉。看守長はその一つをガチャガチャと鍵を鳴らして開けた。何度聞いても、この鍵の音は、私は嫌いだった。地獄の音のようで、悪寒すら感じる。『入れ』十人ほどの女囚がいっせいに頭を上げて、物珍しそうに新入りの私を見た。私にも一目で部屋の様子は見て取れた。ツルツルに光ったコンクリートの床。中央の通路を残して両側に女囚達の座っている棚のような高い板の床。(中略)看守長は部屋の中を見回すと、垢じみた赤い頭巾を被ったタタール人の女に向かって、何か言い残すと、出て行った。あとで判ったことだが、赤頭巾の女、マルーシャは窃盗犯で、彼は私の荷物に手をつけると承知しないぞ、と言いおいたのである。」(p.29)
監房の一日は午前八時の点呼から始まった。裸に近い格好でコンクリートの床に一列に並ぶ女囚達。同じ点呼が夜九時の就寝前にもう一度。その間労役に出される事はなく、室内の床の水洗いだけをさせられた。一日三度の食事はいつも同じで、黒パンが一日600グラム。朝夕はスープが付き、昼は少し硬めの燕麦の粥。スープの実は、塩漬のキャベツとじゃが芋、塩ますの骨で砂糖は一日小さじ一杯だった。胃腸の弱い赤羽さんは、なるべく時間をかけて黒パンを噛んだ。労働はなく、粗末ながら食事は与えられ、寝ることもできる生活ではあったが、想像できない大きな苦しみがあった。それは用便の自由がなかったことだ。監房の扉はそのために一日に二度は開かれたのだが、そう簡単に都合よく排泄ができるわけではない。その限られた時間の中でしか排泄ができないというので、一日中気がかりのまま過ごさなければならなかった。それについて赤羽さんは。「鎖でつながれた家畜でさえ、用便の自由はあるというのに、私たちにはそれもなかった。」と書いている。
しばらくすると三人の日本人が同じ監房に移されてきて、日本人の女性は4人になった。奉天で逮捕されたという川村さん。和服でいた時に逮捕され、そのままの姿で監獄からチタに送られた山本さんと田中さん。二人とも体格は良かったが、田中さんは尋問の時、ひどく投打された結果胸を患うことになった。彼女たちとはつかの間であったが、明るく日本の歌を口ずさむこともできた。三十人以上もの女が詰め込まれている部屋で、パンが日本人女性のパンは抜き取られることが多いのに気づき、四人は一緒に抗議して、その不足分をとり返したこともあった。監視兵が見守る望楼の下で、四人は一緒にせっせと歩き回った。が、やがてそれぞれが別の場所へと移送されることになり、この三人とはすぐに別れが来てしまった。
一人になった赤羽さんは刺繍を始めた。ロシアの女たちは刺繍が好きで、針も糸も禁じられている中でも靴下の糸をほどいたりして刺繍をしたが、その刺繍は赤羽さんのよりずっと稚拙だった。そんな女囚の中には阿片中毒者もいたし、煙草気違いもいた。 梅毒の女もいた。この頃の心情を赤羽さんは次のように描写している。
「私は同房の女囚たちとは、当たらずさわらずの付き合いをし、滅多に喧嘩はしなかった。しんそこから親しくなることもなかった。第一、女囚は移動が激しく、仲良くなった者にも、たちまち別れが襲うのである。親しくなればなるほど、別れとその後に続く寂寥は辛い。何事にも淡々と、運命に身を任せ、流れる水のような心境でいることは、囚人の一つの生き方であった。そうなのだ。嘆き、悩み、怒り狂っても、解決されることはここでは何一つない。私は泣くより笑おうとした。」(p.53-54)
「私がここで半年の間に口にした食べ物は、黒パンとスープ、燕麦の粥、砂糖、この四種類だけなのであった。あとは、ナターシャの差し入れの娑婆の食べ物が少々。ナターシャは嬉しいことに一匙ずつでも差し入れを分けてくれたが、そのため彼女に差し入れがあると、私までが落ち着かなかった。人のものを当てにするとは浅ましいことだ。が、私は浮世の美味しいものを食べたいというよりも、除け者にされることの方が辛かったのである。一匙の牛乳が私にも配られると、私はみなと一緒、という思いに安堵した。食事が粗末だったのは、私たちが虐待されているわけではなく、当時のソ連の暮らしは豊かなものではなかったのである。」
そんなある日、小窓によじのぼると、目の下に三、四十人もの日本人の集団が見えた。捕虜となった日本人兵達だったのだ。言葉をかわすこともできなかったが、突然の懐かしさで胸が一杯になり、「赤羽文子はまだ生きている」と日本の家族に伝えてほしいと切に思った。