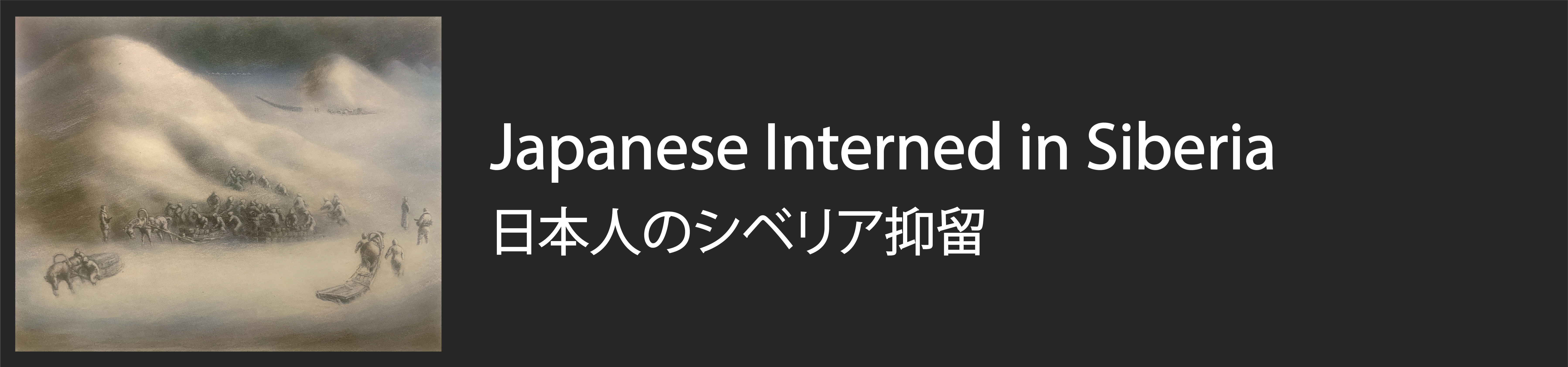様々な人種が入り混じっていたラーゲルの中で赤羽さんはたった一人の日本人ではあったが、その中で、外国文化についてしっかりと観察をしていた。自分の境遇を嘆き悲しんでいるだけだったら、そのようなことはできなかったであろう。冷静に周囲の事実を見つめ、更に客観的な考察を加えることのできた赤羽さんには、時代の先を行く、鋭い感性があったと思う。中でも私はウクライナの女性に関する描写には心を動かされた。私の住むカリフォルニア州サクラメントには宗教弾圧を逃れて米国へ移住したウクライナの人が大勢あり、その人達の新たな米国での生活のために、英語を教えたことがある。赤羽さんの描写は、そんな自分の経験からのウクライナ人の印象と一致して、とても興味深かった。
以下は、p.102〜103よりの抜粋である。「やがて、クリスマスが訪れたが、もとよりラーゲルにはなんの行事もなかった。しかし、ウクライナの娘たちの間には、宗教的な雰囲気が漂っていた。いつもより綺麗な頭巾をかぶり、白いブラウスに黒いサロファン(かたからのスカートの一種)をつけ、三、四人ずつ集まって、澄んだ声で聖歌を歌っていた。この娘たちは大部分、刺繍工場の私の横でクロスステッチをしていた。みなで二、三十人はいただろうか。長い髪をきれいに編んでお下げにし、ある者は冠のように頭の周りに巻きつけていた。その上から白い三角巾をつけて、顎の下で結ぶ。みな品の良い顔立ちで、動作もソ連人よりずっとしとやかだった。彼女たちは故郷で、ウクライナの独立を目指す組織に加わっていたとかで、全員、第五十八条、十年の刑を宣告されていた。ウクライナの父母からは、時々小包が届くので、ほか女囚よりは身ぎれいに装うことができたようだ。肉親からの手紙も度々届いていた。それに読みふける彼女たちの姿は、美しく、羨ましい限りだった。しかし、一ヶ月でも手紙が途絶えると、はた目にも痛ましいほど彼女たちは心配し始める。故郷の肉親に対する政治的、経済的不安は、ウクライナ娘たちの場合、殊に大きいのであった。娘がラーゲルに入ったため、流刑のうきめを見た親もあれば、良い仕事を首になった身内もいる。仲間の中にこうした例を数多く見て来た娘たちは、音信の途絶えをすぐに不幸に結びつけ、心も落ち着かぬ様子であった。そんな娘たちを見ていると、最初は手紙を羨んでいた私も、帰って手紙などには縁のない自分の境遇をよしとするようになった。少なくとも日本では、私がソ連に捕まったからといって、肉親が不幸な目に会うはずはない。むしろ同情されていることを、私は固く信じた。手紙も小包も何も来ないのは寂しかったが、来ないものと諦めてしまえば、もうあれこれと気を回すことはない。可憐なウクライナの娘たちに、私は同情するようになった。」