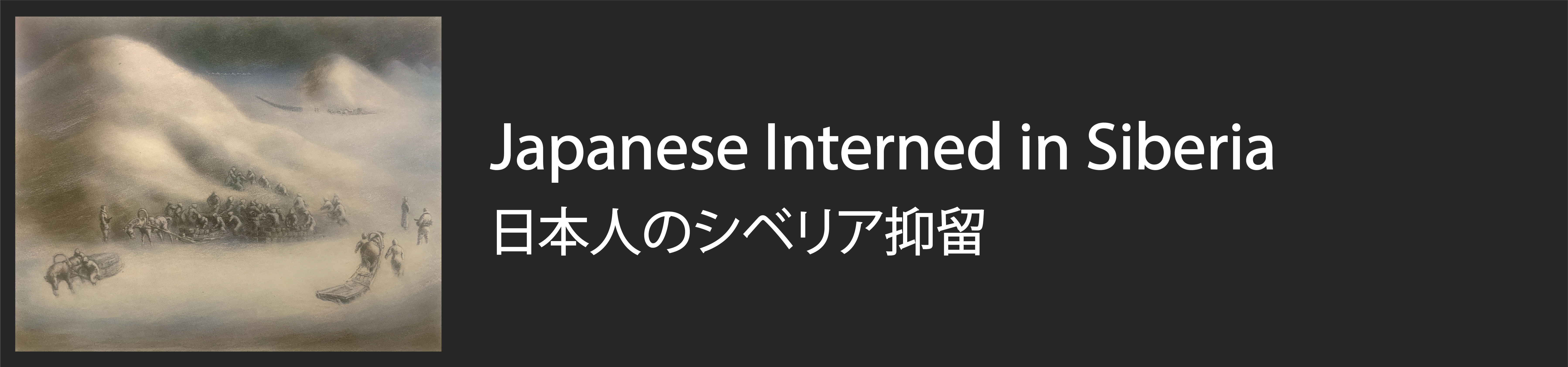雪かきの命令が来たのはある二月のことだった。大雪の中であちこちの道路が寸断されていたのだ。赤間さんは十五歳の時に胸を患って肋骨を二本とり、スコップ一杯の雪さえ持ち上げるのがやっとでとてもそんな重労働ができる体ではなかったので、ラーゲルでは労働はずっと免除されていた。その雪カキのノルマは距離五十メートルのところに幅1メートル、高さ五十センチの道を作ることだった。それでも他の人の半分だったのだ。「私は木のスコップを雪につきさした。三、四回ふり上げると、もう目は霞み、腰はがくがくになった。投げたつもりの雪はあらぬ方に飛んで、道らしいものは一メートルもできない。息だけはずみ、あまりの不甲斐なさに私は呆然とした。」(p.210) そんな赤間さんに配給係りの男はコツを教えてくれた。それで少しは道らしいものができたのだが、ノルマの達成には時間がかかり、陽のくれた大きな森にたった一人残されてしまって、恐怖と焦りから心臓が破裂しそうに高鳴った。ようやく河を見つけ、それに沿って村までがむしゃらに歩いた。「こんな所で死にたくはない。どうしても日本に帰りたい。」と思いながら。
次には貯木場の雪落としの仕事が来た。川岸に何百本も積まれた材木の上に登り、端一メートルの雪を掻き落とす作業だった。丸太の上から転がり落ちたら死んでしまう。が一日十ルーブルの賃金には変えられなかった。滑らぬよう気をつけながらスコップで雪掻き落とす。赤羽さんはただ黙々と作業を続けた。他の人が休んでいる間も働き続けてようやく仲間の速度に追いついた時、赤羽さんにはある感動がこみ上げて来た。
「私はしばらく、胸が一杯になって、かき取られた雪の下から現れた煉瓦色の木の肌を、半ば恍惚と見つめていた。こんな重労働ができたことが、私には夢のようだった。体操の時間さえ休まねばならなかった私が、零下三十五度のシベリアで、男のように頑丈なソ連の女に混じって働いていている!働けるのだ!立派に!私は雪の上に滑り降りた。丸太に背を寄せると、熱いものが目にこみあげてくるのを感じた。嬉しさとともに、私の心は感謝で一杯になった。私に、こんな力を授けてくれた目に見えぬ大きな力に。」(p.214)
『ありがとうございます。神様、私にもできました!力を与えて下さった貴方に感謝いたします!』その神が何であるかは、私にもわからなかったが、この時ほど私の心が祈りと感謝で満たされたことはなかった。私はしばらく、雪の上にひざまずいたままだった。大連時代、母がやかましく私に信仰をすすめていたことが思いだされた。私の弱い身体を、信仰によって少しでも良くしたいという母の願いであった。私はそれが煩わしく、よく母と衝突し、結局は母の意志には従わなかった。奇しくも、母から遠く離れてしまった今、私は祈りの心をてんから教えられたのであった。」(p.215)
ここを読んだ時、私の眼はこみあげてくる涙で一杯になった。身に覚えのない罪で自由を奪われ、家族とも日本人からも離され、たった一人外国人たちの中で、しかも厳寒の考えられない最悪の環境で先も見えないまま命からがら生きて来た小さな女性の、一体どこから、このような感謝が沸き起こったのだろう。華奢で病弱の体には耐えられないような労働を課されたのに、それに対する憤慨などは微塵も見せない。そして、ただただどのようにその試練を乗り越えられるかと、そのことだけに集中した純粋で勤勉な精神の美しさを私は感じた。「赤間さん、ノルマが達成できて、本当によかったですね。」と言いたかった。人には色々な側面があるが、苦境に立たされた時にこそ、人間の本質が試される。そこに気高い精神を見た時の感動は心を揺さぶる。シベリア抑留の苦渋の記録の中から、このような光を見つけたことは実に宝物に出逢ったようであった。
その後も色々な仕事が回って来ると、赤羽さんは生きるために、どれも一生懸命にこなした。村や森に貼る掲示板を書く「看板書き」の仕事。ソ連人が書いた間違いだらけの看板とは違って、丁寧に仕上がった看板は評判となった。リューマチの痛みを我慢しながら、雪落としや刺繍は続けた。冬を越えるための大切なじゃが芋の植え付けもあった。このような労働と、栄養不足とリューマチで、老婆のような姿になってしまった。