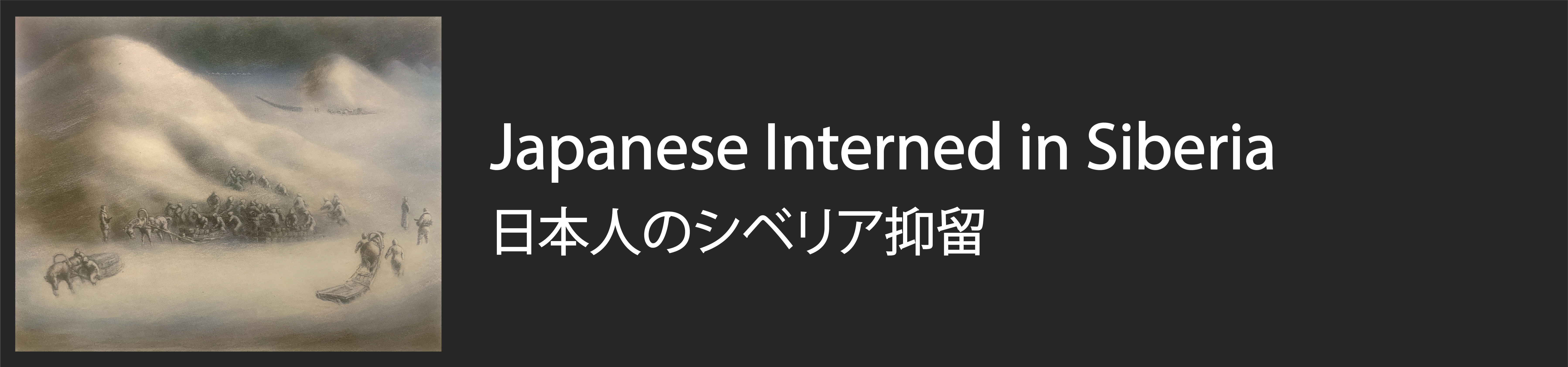村に生きて帰れたのは奇跡のようだった。が、スパイにはならなかった事を人に知られないように本当に気をつけた。さて、夏になって仕事が途切れ、重労働の「丸太ころがし」をやらなくてはならなくなった。貯木場に積まれた赤松を川に落し、川下に流すのだ。小枝のような体は、丸太に押しつぶされそうだ。丸太は直径二十センチから八十センチまで色々で、三人で押して川は流す。それでも動かぬ時には棍棒をテコ代わりに使った。そこには蚊とブヨの大群がいて、むき出しの腕は刺されて真っ赤に腫れあがり、目も開けていられない。
次の仕事は月給二百四十ルーブルの便所掃除婦。「娑婆にいた頃には、便所掃除婦など、考えられもしなかったが、此処では何の感慨もなく、平気で仕事に取り組んでいけた。生きて行かねば、収入を得なければ、という厳しさの前に、仕事の貴賎など問題ではなかったのである。」(p.244) と赤羽さんは書いている。便所はラーゲル式に、板に切った丸い穴が五つ六つ(時には一つだけ)並んだもの。仕事は、穴の周りの汚物をスコップで落し込み、あとを箒で掃いておくことであった。しかし紙もなく、生活程度の低い森に木樵たちは所かまわず手についた汚物を擦りつけて、公共の場所をきれいに使おうという意識はまるでなかった。しかも村の子供たちはそんな仕事をする赤羽さんをひどくからかって、それには閉口させられた。「便所掃除は汚い仕事で、粗末な衣服に箒を担いだ私の姿は哀れなものであった。しかし、私は嘆きはしなかった。ここは仮の生活だ。今いる自分は仮の姿だ。私には本来の、私の住むべきもっと良い世界がある。そこへいつかは帰っていける。いや、きっと帰るのだ。誰にも言わなかったが、私はこんな思いを、絶えず心に呟き続けていた。」(p.245) ここでもまた、赤羽さんは孤高の人として自身の人生の行く手を見据え、自己の魂を守り、育てるのに専心することで、現実の世界の試練に打ち勝っていた。
流刑人のマキシム•ニコライヴィッチは50歳をすぎていたが、土地の女であるニューラと結婚して七ヶ月になる娘ネリーが生まれていた。二人は八月に草刈りに行かねばならなかったので、可愛いネリーの子守を赤羽さんに頼んだ。報酬は夕飯だけだったが、子守は楽だったし、ネリーが寝つけば、家の裏手の草の茂みで全身の日光浴ができた。これはリュウマチに良さそうだった。ニコライヴィッチは流刑になる前には相当の生活をしていたらしく、教養もあった。だが妻のニューラは村人で無教養であったので、寂しいらしく、そのうさを酒で紛らわしているようであった。彼は赤羽さんの看板描きの仕事になくてはならない人で、森に立てる掲示板の原稿は彼が皆書いてくれた。しかし彼はある寒い冬の日に川で溺れて死んでしまった。もう彼は故郷へは帰れない。この事件は必ず生きて日本に帰るつもりだった赤羽さんを滅入らせた。
皆が祝日にウオッカを飲み楽しみに浸る時、赤羽さんはそれにとけ込めなかった。そんなある時、一人で河におり水を見ていると、暗黒色の水底から何かに招かれていたような気がした。そこで静かに凍死する自分を考えた。もう苦痛は終わる、辛い毎日の生活もない….ハッとして我に帰り青空を見上げると、日本の肉親の顔が浮かんだ。その時、何年経とうと自分を待っていてくれる肉親のために、頑張らなければならない、と思い直したのだった。
春の訪れと共に凍っていた河が動き出した。大地が動くような壮大な光景。そして四月が来て、じゃがいもとキャベツの季節がやって来た。シベリアでは野菜で手に入るのはこの二種類だけだった。夏には自然の野ぶどうが手に入った。赤羽さんは仕事はスローガンを書く看板書きを必死に続けたのだが、二度目の革命記念日が来た頃には一ルーブルも賃金がもらえなくなって困った。赤羽さんは日本人でソ連の共産党員ではないのに、「社会的な責務を果たしただけだ」と取り合ってもらえなかったのだ。それから少しすると便所掃除の仕事さえもなくなってしまった。かろうじて託児所の保母の仕事が舞い込んで来て、それで命をつなぎ、あとは八月までにかけて森での丸太ころがしの労働に駆り立てられた。いつもこのようなギリギリの状況で少しばかりの生活費を得、かろうじて暮らしを繋いでいたのだった。